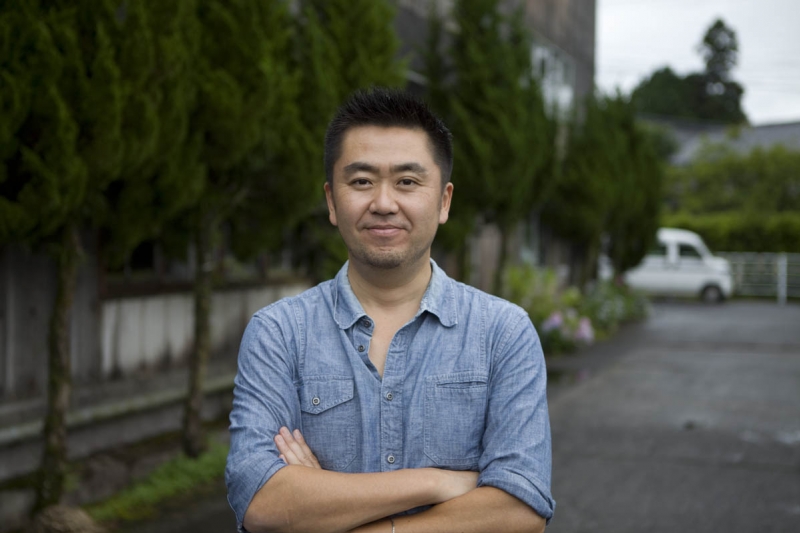Interview: 青山窯 川副史郎
「2016/」に参画する窯元の一つ、青山窯。もとは有田ではなく伊万里市に窯を持ち、歴史をたどると鍋島藩とゆかりのある窯元。鍋島様式という型を重んじつつも、「2016/」という型を壊すことに挑戦した想い、「2016/」を通して学んだこと、得たものについて川副青山の代表取締役 川副史郎さんに聞いた。
- 青山窯は歴史をたどると鍋島藩ともゆかりのある窯元であり、器の表面に余白がないほど絵付けを施す技術で有名です。しかし、「2016/」で発表したコレクションは絵付けが見られない真っ白のコレクション。青山窯のもつイメージとは随分異なります。なぜこうしたアイテムを作ることになったのですか?
今後の伝統工芸のあり方などに悩みを抱えていた頃、ちょうど「2016/の公募があると声をかけてもらいました。なので「2016/」には自分では発想できない、まったく新しいことにチャレンジして視野を広げようという気持ちで臨みました。結果、ステファン・ディーツとの協働では絵付けもなく、青磁でもない、というこれまでの青山窯では考えられない商品を作ることになったのです。また経営面でも、これまでの青山窯は少量生産で店舗での直売をメインとしてきましたが、「2016/」ではスタンダードなテーブルウェアを量産することが求められ、自分の中での意識改革が必要でした。
- ステファン・ディーツとのコレクションは青山窯だから実現できた形なのでしょうか?
青山窯だからというよりは、我々と取り引きのある地元の職人たちの技術を取り込んだデザインになっていると思います。青山窯の製造システムをフルに生かしたデザインとでも言えるかもしれません。有田の窯業は分業化されていて、石膏型をつくる型屋さん、その型を持ち込んで土から形状を作る生地屋さん、そして我々窯元の協働によって磁器が生まれます。ですから協力会社と私のノウハウを集約してものづくりに取り組んでいくわけですが、「2016/」で大変だったのはディーツが作りたいという形が26形状と、他のデザイナーに比べて飛びぬけて多かったこと。焼き物は焼成時に収縮するために、生地を薄くすればするほど変形のリスクを伴います。ディーツのデザインはすべてがベタ底で日本の焼き物の伝統的な形である高台がないために、収縮の力が製品全体に伝わりやすく、淵も薄い。26形状、それぞれの形に合わせて収縮の調整を行うことになり、製作は困難を極めました。加えて形に対するディーツからの要求は想定以上で、ドイツ人らしく厚みについてなどを1ミリ以下のチェックが入るのです。約1年半、私はこのプロジェクトだけに専念して、「2016/」以外の他の仕事は工房のスタッフ任せでした。
-「2016/」プロジェクトにどのような意気込みで臨んでいますか?
父が大川内山から伊万里市に移転した工房は47年間操業しました。そして今回、量産に対応できるようにするため、有田焼工業協同組合内に窯を移転しました。以前の工房では窯が古かったので量産体制に不安がありました。組合では生産効率の良いトンネル窯を弊社も入れて5窯元で協働操業しています。台車に製品を積んでボタンを押せば自動的にトンネル状の窯に入っていきますが、1300℃という高温で焼成しているので移転前のテストでもこれまでの窯とまったく遜色なく仕上がりました。また同じ敷地内に圧力成型の工場もあるので生地供給の不安も払拭されました。それでも移転は大きな決断でした。それによってスタッフも変わりましたし、環境も変わりました。協力してくれる人もたくさん増えました。まるで創業したかのようです。冗談のようですが、実は最初は「ミラノサローネ」に行きたいなくらいの軽い気持ちだったのですが、今では会社を変えて進化させるきっかけにできるように全力を挙げて頑張っています。
- このプロジェクトを通して学んだこと、得たことは何でしょう?
私自身絵付けもしますし、鍋島焼の伝統的な作品が大好きです。素晴らしい絵柄や形状は300~400年前に革新的な挑戦があってこそ生まれたと思います。このプロジェクトを通して、勇気をもって1歩踏み出せばまったく違う世界が広がっていることが分かりました。 今後、100年後、200年後も焼き物の伝統文化を残していくためにも、日々新たな挑戦の積み重ねが必要だと確信しました。